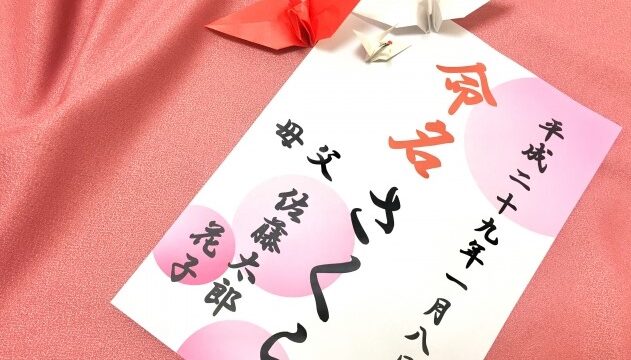日本で無痛分娩したいというと必ず誰かが「危険でしょ?!」「痛みが無いなんて愛情が持てないよ」「普通に産めば?」「どうして無痛にしたいの?」などと言われたり、質問攻めにあうこともあるかもしれません。
一般的な健康な妊婦は希望しても希望通り無痛分娩にすんなり行かない事もあるでしょう。日本の妊婦に選択肢はないといっもいいかもしてません。
今回、無痛分娩とは?無痛分娩の方法、日本で無痛分娩が進まない理由を記事にしました。
無痛分娩は危ないのか?
『日本産科麻酔学会』のHPを参考にしています
♦無痛分娩とは?
硬膜外鎮痛と、点滴からの鎮痛薬投与があります。硬膜外鎮痛では、硬膜外腔という背中の脊髄の近い場所に、局所麻酔薬を使用する方法と点滴からの鎮痛では静脈の中に医療用麻薬を投与し、痛みを和らげます。
硬膜外腔という場所に注入された薬は、硬膜外腔の周囲の神経に作用します。 そして子宮や腟、外陰部、会陰部からの痛みを伝える神経遮断し、お産の痛みを抑えます。
硬膜外麻酔は無痛分娩以外の手術や処置でも使われています。
知識と経験のある医師が行えば危険な物ではありません。
ただ以下に書いた問題もあります。
♦日本で無痛分娩を希望しても・・・
日本には約2800の分娩施設があるそうです。そのうち希望があるときに硬膜外無痛分娩を行う施設は250足らずだそうです。
時代の流れが無痛分娩希望でも、現実的に麻酔科医が少ないため産婦人科のような24時間体制が対応できないから現実的には厳しく日本では無痛分娩の数は増えません。
無痛分娩を希望している妊婦さんがいる場合、安全に無痛分娩を受けられるように、計画的に分娩を進める場合があります。それは、本来は陣痛が来てから麻酔をかければいいのですが、上記に書いたように、麻酔をかけられる医師がその時に必ずいるとは限りません。なので、日本では計画的に無痛分娩を行うことが多いです。
海外では無痛分娩が主流になっています。
知識と経験の十分な医師のいる施設で無痛分娩を受けることをお勧めしますと『日本産科麻酔学会』のHPでも言っています。
どうしても無痛分娩がいい!どうしたらいい?
今、通院している産科が無痛分娩をしていない。という場合はできれば妊娠32週より前に相談するのがいいですね。
『無痛分娩しています』と看板をだしている産科でも、希望するならば早いうちに伝えたほうがいいです。
無痛分娩を希望すれば方法やその利点、欠点などについて、妊婦さんと医療スタッフが事前に話し合いをします。
産科により無痛分娩のやり方が違うこともありますので直前になって話が違う、こんなはずじゃなかったと後悔しないためにも、十分な説明を聞いて納得した上で無痛分娩を受けるのがいいですね。
もう一つ、無痛分娩を行う医師が、妊婦さんの体の状態を事前に知っておくと、安全でスムーズ行いやすくなることです。
妊婦さんの病気になどによっては無痛分娩が受けられない場合もあります。

実際の無痛分娩の流れ
予定した計画分娩の日(日本は無痛分娩に対応できる医師が少なく、24時間体制ではないので陣痛来てから無痛分娩開始というのは難しいようです。フランス、アメリカは無痛分娩が主流でフランスは出産全体の8割アメリカ6割が無痛分娩を選びます。なので医師の数も多く、麻酔経験も豊富な意思が陣痛が来てから麻酔を開始することができます。日本は確実に経験豊富な医師を確保するために予定の日を決める所が多いです)
妊婦さんい横向きになってもらい腰から太目の針を刺して硬膜外の管を入れます。
硬膜外鎮痛の場合、硬膜外の管から薬を注入すると20~30分で鎮痛効果が現れます。 効果が現れ始めたときには、陣痛が弱くなった、短くなったと感じることもあります。 徐々にお腹が張っているのに痛みがなくなっていることに気づくと思います。 同時に足が軽くしびれた感じがあるかもしれません。
脊髄くも膜下硬膜外併用鎮痛は鎮痛効果が数分で現れます。どちらの麻酔も硬膜外の管が入ったあとは注入のポンプを用いて薬を持続的に注入すていきます。手動で痛みを調節するやり方もあります。施設によって違いがあります。
内診で卵膜剥離をします。子宮壁から卵膜を刺激します。子宮口が2~3センチ広がったらバルンを入れてさらに広げます。
あとは自然分娩と同じ様にいきみます。麻酔の影響でいきみが弱くなる人もいるようです。痛みはありませんが、生まれた時はもちろん意識もあります。
自然分娩と同じように感動できます♪自然分娩のように疲労感がない分赤ちゃんに余裕をもって接することができるかもしれません(∩´∀`)∩
赤ちゃんに麻酔の影響はない?!
1980年代の硬膜外無痛分娩では、現在一般的に使用されているよりも高い濃度の局所麻酔薬を使用していたそうです。この麻酔で生まれt赤ちゃんは生後数日間、運動機能や刺激に対する方位反応が劣ったという研究発表もあったそうです。
現在主流の硬膜外鎮痛は、低濃度の局所麻酔薬に少量の医療用麻薬を加えて持続的に投与する方法で、生まれた赤ちゃんに自然分娩の赤ちゃんと比べても反応やアプガースコアに差がないことがわかりました。
しかし、妊婦のお母さんに麻酔の量が通常より多い量が使用された場合、24時間以内の赤ちゃんの反応や運動機能が、少ない量の投与の赤ちゃんより低かったという研究結果もあるそうです。
全く影響がないわけでは無いので、無痛分娩希望の場合は、無痛分娩件数の多い、慣れた医師のもとで行うのがよさそうですね。

無痛分娩は費用が高い?
自然分娩の費用は保険適応外ですので40万円前後で、自治体などから補助金が出るのを使用すればほとんど、お金はかからないことが多いです。
無痛分娩は個人院の方が安く<総合病院<大学病院と高くなるようです。
無痛分娩は大体出産+プラス5万円から20万円のようです。出産した施設に確認してください。
無痛分娩のメリットとは?
♦痛みを軽減できる
♦赤ちゃんへの酸素が減らない
♦落ち着いて出産に望める
♦産後の回復が早い
♦高齢出産のリスクがさがる
年齢を重ねるにつれて体力は低下します。私は高齢出産で自然分娩でしたが本当に体力がなかったです。24時間子育てが始まるわけですから無痛分娩で体力を温存しながら出産できるのはいいと今なら思います(;^_^A

無痛分娩のデメリットとは?
♦陣痛促進剤による合併症リスクが増える
麻酔によりいきみが弱くなってしまうことがあります。陣痛促進剤で人工的に陣痛を起こすことで、子宮が強く収縮します。胎児が圧迫されて胎児機能不全に陥ったり、子宮破裂が起こることがあります。
♦吸引分娩や帝王切開になるリスクが高い
陣痛が弱くなることや、上手くいきめないことでお産がスムーズに進まないこともあります。そのため吸引分娩や帝王切開になることもあります。
♦母乳育児率が減る
無痛分娩では、人工のオキシトシンを含む陣痛促進剤を使用するため、ママの体内で自然に作られるオキシトシンが減ることもあり、それにより母乳の分泌が減少すると考えられています。
無痛分娩の事故と今後
2018年3月29日に厚生労働省の研究班が無痛分娩の安全対策で初提言しました。これは法的なものではなく任意だそうです。
内容は一部です。
・麻酔を担当する医師は定期的(2年に1回程度)に研修を受講する
・麻酔を担当する医師は、麻酔後30分は近くに待機。
・医療機関は麻酔管理者の配置など十分な人員体制を敷く
・マニュアルを整備し、情報を公開すること
・医師の研修強化産科麻酔の研修体制を作る
・技術に習熟した医師の認定制度の是非を検討する
・具体化を進めるため新しいグループを設置する
などなど
この少し前に起きた無痛分娩の死亡事故にかかわった医師は【1人の産科医による出産と麻酔の兼務を認める】という内容だという。つまり、専用の麻酔科医はいない状態で無痛分娩を実施したことになります。研究班に参加した麻酔科の医師は「兼務しないのが理想だが、まずは誰でもやれる体制作りをし、少しずつ、より安全な方向に行くことが重要」とはなしたそうです。う~ん・・・。
私も手術室にかかわる看護師ですが、田舎の病院で医師不足により、専用の麻酔科医はいません。改めて麻酔科医もいた方が安心だと思いました(-_-;)
最後に
日本は無痛分娩の割合は全出産の2.3%と低いです。
まだまだ自由に安全に出産のスタイルを選ぶのは遠い道のりに見えますね。早く安全・安心に無痛分娩も出来るように発展していくといいなぁと思いました。
関連記事 海外の出産事情↓