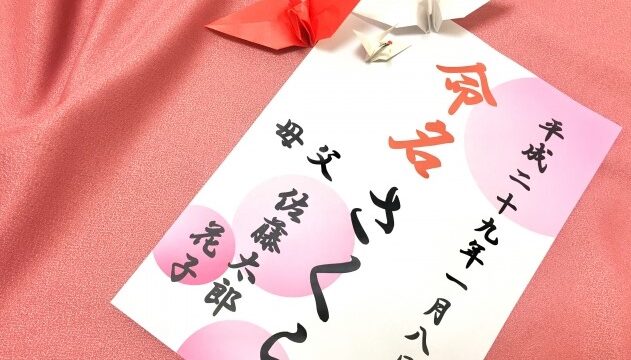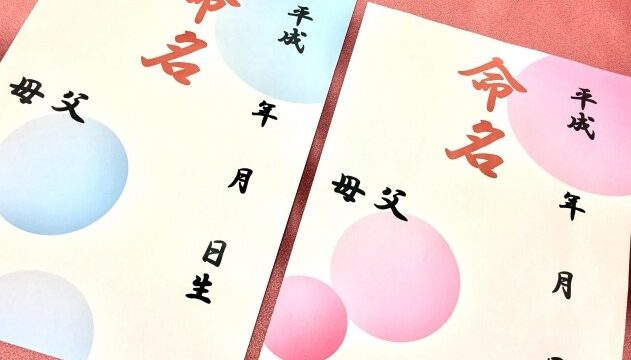楽しみなクリスマス♪
家族でクリスマスツリーを飾るのも楽しみの1つですよね♪
今回クリスマスツリーの始まりは?
クリスマスツリーはなぜモミの木なのか?
気になって調べてみました。
クリスマスツリーの始まりは?
現代のようにクリスマスツリーを飾るという習慣は、ドイツからと言われています。
ドイツから世界に広まったと言われています。
現在でもオーナメントやモミの木を買えるドイツのクリスマス市場は、とっても有名ですね。

昔のドイツでは、年末に木を飾る習慣があり、枝には色紙やリンゴ、お菓子で作られた薔薇などが飾られていました。
でも、そもそもの始まりは何でしょか?
色々な説がありますがココでは有力と思われる説を紹介します。(諸説あります)
古代ヨーロッパ北部、北欧ゲルマン民族の間で行われていた冬至に行われる「ユール」というお祭りが元という説です。
キリスト教がまだできる前の話。
北欧では冬至の頃は昼でも暗く極夜の状態が続くので、早く太陽がまた出るようにと始めたのがユールというお祭りです。
ユール祭りでは、北欧神話の神々にお供え物をして、みんなで飲み食いをしてお祝いをしました。
また冬至には魔女や悪魔、霊などが現れると考えられているので、悪いことがおこらないよう、ご馳走などを用意していたんです。
このお祭りでは、森で木を切ってきて、家へ運ぶという習わしがありました。そして、その木の幹を燃やして、冬至の暗い時期に太陽の光を想うのです。
これがクリスマスツリーの大元の始まりではないかと言われています。
そのあとゲルマン民族が南下して、ドイツなど他の地域にもこういった習慣が伝わったといいます。

キリスト教がこの習慣を取り入れていきます。
うまくキリスト教の教えの中に取り込みながら、布教していきました。
その結果、もともとキリスト教徒は関係のなかった冬至の行事に、キリスト教の教えの意味をもたせましたのです。
三角形のクリスマスツリーの形を、「父と子と精霊」に当てはめたようです。
なぜクリスマスツリーはモミの木?
日本など多くの国では、クリスマスツリーといえば「もみの木」ですね。
なぜモミの木?なのでしょう?

ヨーロッパではこんな説
昔、冬の時期を過ごす人たちにとって、1年中緑の木々(常緑樹)は特別な存在でした。
そして、常緑樹の枝が幽霊や魔女。悪霊などを追い払うと信じられていたので、窓辺に飾ったりしていました。

ですから海外では、クリスマスツリーの木は、冬に葉の落ちない常緑の針葉樹であれば何でも良いと考えられていもいるようです。
モミの木も種類がたくさんありますしね。
日本ではありえないと思いましが松の木も使われることもあると私も知りました。
モミの木にはラテン語で「永遠の生命」という意味があり、考え方としては同じといえますね。
ドイツ地方ではこんな説
モミの木には小人が宿っている。
食べ物や花を飾ることで小人がそこへ留まり、力を与えてくれると言われている。
クリスマスツリーとして用いられるようになったと言われています。
キリスト教、アダムとエヴァ説
「アダムとエヴァの堕罪」の舞台で知恵の樹として使われるリンゴの木がですが、冬は葉が落ちてしまう。
モミの木なら枯れたり落ちたりしない。
リンゴの代わりにモミの木にリンゴを飾った事からモミの木になったといいます。
まとめ
家族でクリスマスツリーの意味を話しながら飾るのも良いですね♪
今年のクリスマスは、クリスマスツリーの由来となった、遠い昔のお祭りに心を馳せてみてくださいね!
楽しいクリスマスシーズンをお過ごしください!
合わせて読みたい記事
クリスマスツリーのオーナメント意味少し怖い?本当の意味とは?